老齢になっても本当に若者に勝てるの?という疑問への考察(3)
さて、前回の続きであるが、かつての同門の先輩にして朋友、宗有と亨の対決はいかなる決着みたのであろうか?
ここからが彼にとって望むべくして臨んだ本当の修業の始まりだったのかもしれない。
白井 亨、兵法開眼への道のり
さて、以下は亨の弁である。
私は、木剣を持って彼と対峙した。彼もまた木剣を持ち相対した。私は即座に前に進むとともに、一瞬の内に相手の機先を制するがごとく、切っ先に一閃して打ち込み、彼の心の奥底を知ろうとしかけた。
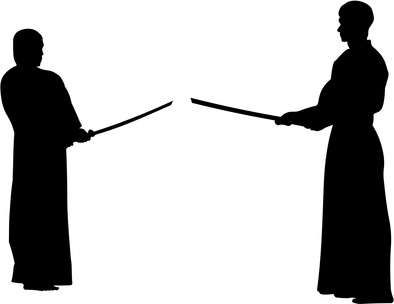
しかし彼は全く動ぜず落ち着いており、その仕掛けに応じない。
するとあっとう間に私の木剣を頭上に飛ばして、眼前にて私の全身をおおうがごとく立っていた。

まるで夢のようであった。
手足の力はぬけ、大汗が全身を流れ落ち、驚嘆するとともに気が付けば、私はいつのまにか膝を屈して、頭をたれていた。
これこそ亨の疑念を霧消させる兵法の真骨頂ではあるまいか。老者が太刀を執って従容と騒がず、慌てず、相手を制圧してしまう。
今、それを見た!
そこで亨は、改めて訊ねた。
「あなたの精妙な術は、いったいどのようにして会得なされたのか?」
「見性得悟の一念のみ」
と、宗有はこういった。
※見性(けんしょう)とは、人間に本来そなわる、本性を徹見すること。禅の悟りの1つとされる。得悟(とくご)は、悟りを開いて真理を会得すること。
「そなたは、以前習得した技をもって、諸国を廻り、仕合をして歩いたのであろうが、それは邪念を増すばかりである。そのようでは、たとえ年月を重ねても、なんの役にも立たないものだ。世の中には、壮気あふれる者、技の優れた者などがいて、面、小手、竹刀を担ぎ、肩を怒らして歩いているのをよく見る。
そのたびに、いたずらに妄想邪念を積み、ただ年を経ていくのだなと、そぞろ憐れに思うのである。」
亨は怖れ入り、汗びっしょりになった。
亨はその場で、宗有の膝下に入門を乞い、許される。
二人が師弟のちぎりを結ぶ一瞬だった。
宗有は、白隠禅師(臨済宗中興の祖と称される江戸中期の禅僧)の高弟、東嶺和尚に参禅し、<天真に通ず>との印可を得ている。
※「天真」とは、生まれた時の純真さを失わず、偽りや飾りけがない様子。
※印可(いんか)とは、師がその道に熟達した弟子に与える許可のこと。 その証として作成される書面は印可状と呼ばれる。いわゆる“お墨付き”のこと。
その兵法の道はそして、「見性得悟」だった。
宗有は、亨に説いた。
「そなたは、幼い頃から二十余年、邪道邪念の兵法を学んだ。それらが五体に凝り固まっているだろう。以後は魚鳥の肉を摂らず、日夜清水を浴び、清浄無垢の心身になり替わること」
宗有は、比喩として言ったのかもしれないが、亨は正直にその教えを守り、肉を摂らず、極寒を嫌わず、水行に励んだ。そのため、体力、神経をひどく痛めたこともある。
いずれにせよ、新たな兵法の道を目指して、ひたすら心身を苦しめるほど修行に励み努め続けた。
そのようなたゆまない努力を続ける中、すでに亨は中西門を代表する剣士になっていた。
文化十二年(1815年)の八月、宗有は大阪城代を命ぜられた主君、高崎藩主に従って、大阪に行くことになった。
そのとき宗有は、亨に、
「そなたの兵法はすでに道を成している。もはやわが道統は絶えることあるまい。」
といって、天真伝の印可を与えた。それは同時に亨が「天真伝一刀流」を継ぐことでもあった。
亨はさらに、異色の念仏行者と言われた「徳本行者(江戸時代後期の浄土宗の僧、徳本上人とも呼ばれる)」について修行を重ねる。
徳本は紀州の生まれで、4歳の時から生涯かかさず、念仏唱名を怠らなかった人物である。水垢離、断食はむろんのこと、念仏を唱えながら、五体を大地に叩きつける荒行を続け、昼夜無限の「念仏行」を行なった。
亨が徳本行者の道場で得たものは、身・体・意の一致である。
「上人の体を見るに、手はことさら動いていない。自然活動の妙は、唱名と手と天機と一致したるに、釈然として会得ができた」(「日本剣道史」)という。
これはとりもなおさず、気・剣・体の一致である。
「試みに、木剣を手にしてその意にならえば、意外にも、不思議にも至妙の機を自得したのである」(同書)
すなわち、亨の兵法開眼である。

言うまでもないことだが、徳本行者の一挙動をぼんやり見て悟ったわけではない。
若い頃から疑念の一つ一つを、刻苦奮励しつつ克復し、たゆまぬ修行の積み重ねがあったからこそである。
亨はその成果を、<天真嚇機>と称した。
ひたすら丹田を練り、真空に参じて五体を忘れるとき、ひとりでに剣尖から火輪を発せずにはおかないのである。
それゆえ、かれの一刀流の解釈は、
「一刀流と称する者は、一刀截断(いっとうせつだん)の義に非ず。仏典にいわゆる阿字の一刀なり」
※「截断」とは物をたちきること。
「阿字」とは、密教教義上、生滅のない根源的な実在を指す。兵法の道は、体力でもなければ技術でもない。不生不滅の嚇機であり、それが一刀の鋒先を通じて発するところにあるのである。
さて、天保のはじめ、九州から大石進(おおいしすすむ)が、五尺三寸(約160センチ)の大竹刀をひっさげて、江戸に登場し、剣界を圧倒する。
※大石進・・天をつくような巨漢だったと言われ、二メートル十二センチもあったと言われる。
その勝負付は、諸説あって一定しないが、当時名声を誇っていた男谷精一郎、千葉周作、桃井春蔵といった江戸の大道場を代表する剣士以下、みな一種の恐慌をきたしたのは事実である。
のちに勝海舟は、「ご維新以上の騒ぎ」とまでいったほどで、大石は江戸の名だたる道場に勝負を挑み、荒らしまくった。
その時の大竹刀による勝利がしばらく影響して江戸の剣士の竹刀が一様に長くなったほどだ。
その中でただ一人、明らかに勝ったのが、白井亨だった。
ときに大石、三十七歳、亨は五十一歳である。
亨にとっては相手の得物が三尺であれ、五尺であれ、なんの変わりもない。ただ一刀の鉾先から発する嚇機で闘えばよかったのだから。
もっとも勝ち負けそのものにも超越していたことだろう。
直心影流の伝承者、第15代の山田次郎吉は、その著「日本剣道史」に、
「白井の如き、実に二百年来の名人なり」
という言葉を書き記している。
60代でも強かった達人は確かに存在した
いかがだったろうか?
ご覧の通り、実は彼が師事した宗有もまた六十三歳にして三百人に剣技を教えてすでに強者である二十代の亨に勝っているのだ。
白井亨が若い頃、見知った剣の強者たちは皆40代でその実力は落ちていき、50代という老年期になるともはやその剣技は活用できるレベルではなくなっていたとあったが、江戸時代の50代は、今の70代と言っていい。
医療も現代には到底及ばず、暖房、冷房もなく、食事も今のように栄養価の高いものは食べられず、農民や職人は肉体労働、武士も戦うための訓練で体を酷使するため、人生50~60年の時代だからだ。
そんな時代に、宗有も亨も60代になっても、若者に負けない強さを維持したと史実として記録に残っているのだから心強い。
この話の中でポイントはやはり現代剣道でも言われる気・剣・体の一致だった。
どうやら心の修養が最後はキーとなるようだ。
勝負に勝つには、気は充実させつつも自分の心は常に平静でいて、相手の所為によっても動ずることなく、相手の心を見切り、一瞬の隙を作るなり、見抜くなりして勝つ。
若い頃は血気さかんであるから、相手が強いほどやっきになって反撃してしまうし、逆に臆することもあるが、修行を重ね老境に達するともはや欲や邪念は消え去り、まさに明鏡止水の境地に至るのだろう。
言葉でいうのはたやすいが、これを常に具現化できる人間はわずかだと思う。
他にも80歳まで生きた柳生新陰流継承者、柳生石舟斎も60代においても無刀取りを家康の前で、木刀を持った五男の柳生宗矩(24歳)相手に披露するなど、強かった。
この時まだ53歳だった家康も自身の剣技に自信があったので、我が剣を受けてみよと勝負を挑んだが、石舟斎の無刀取りに完敗したという。
▼以下参照サイト
戦国武将列伝Ω「柳生石舟斎と柳生宗矩~柳生新陰流「天下統御の剣」~治国平天下」
なんともわくわくしてきませんか?
中年になって体力が衰えてきたと嘆いている人も少しは希望が見えてきたと言いますか、元気づけられたのではないでしょうか?
さて次回は、また近代に戻って、その老齢期においても強かったという持田盛二先生を紹介したいと思います。


















