「「剣道三倍段」の真実
さて、ここではちまたでよく話題になる「剣道三倍段」について取り上げてみたいと思います。
これは剣道をしていた者であれば一度は仲間内で話題になったことがあるはず。
いろいろ調べていくうちに興味深い事実も見えてきました。
「剣道三倍段」とは
今一般に知られている「剣道三倍段」とは、「武器を持っている剣道に対して、無手の空手や柔道などの武道をしているものが相対する時は、段位としては三倍の技量(例えば剣道初段に対して空手三段など)が必要」というもの。
しかし本来の意味は、
「武器術において、槍術(または薙刀)を相手にするために剣術の使い手は三倍の技量(三倍の段に相当する実力)が必要である」
ということだそうです。なので「剣術三倍段」と言う方が正しいでしょう。
つまり意味的には以下の二点が一般的に知られている意味とは異なります。
<一般的に知られている意味>
・剣道に対して無手の空手や柔道等で戦う場合、段位で言うなら三倍の技量が必要
・「剣道」対「無手の空手や柔道等」
<本来の意味>
・槍や薙刀に対して剣術で戦う場合、段位で言うなら三倍の技量が必要
・「剣術」対「槍や薙刀といった長物の武器」
となると槍や薙刀に無手の空手や柔道が立ち向かうにはとんでもないほどの技量の差が必要ってことですね(汗;)
そう考えるとローマ帝国の重装歩兵が長槍を使っていて非常に強かったというのもうなずけるってもんです。
日本の戦国時代でも、その時代のドラマを見ると歩兵は長槍を持っているシーンがよく見られていておなじみですが納得って感じです。
意味が変わった理由
冒頭の解釈が一般に広まった契機としては、1971年から6年間、週刊少年マガジンに連載され人気を博した「空手バカ一代」という漫画で、剣道は武器を持っているため剣道初段に対し、空手三段で互角だとして「剣道三倍段」という言葉が使われたことが発端と言われています。
これは極真会館 設立者である、大山倍達氏を主人公にした物語なのですが、その絵柄や作中の雰囲気は以下のサイトを参照されるといいでしょう。
> 拳の眼
私はリアルタイムで全巻読んだわけでもありませんが、実写映画化などもされ昭和世代で武道や格闘技好きなら知らない人はいないのではないかと思われるほど有名な漫画です。
漫画は「後ろの百太郎」や「恐怖新聞」といったホラー漫画で有名なつのだじろう氏によるものなので、絵柄もちょっと怖い雰囲気でかなりインパクトがあります(笑)。
この作品で使われた「剣道三倍段」説は、作者の梶原一騎氏が創作したものなので、実際検証されたわけでもなければ昔の武道関係者の中で通説だったわけでもありません。
しかし普通に考えてもおかしくない理屈ですし、当時大山倍達氏の存在はカリスマ化していたので非常に説得力がありました。
そのため広まったのでしょう。
では本来の意味の槍や薙刀が剣術の三倍強いって話は本当でしょうか?
もう少し調べてみたところ、こちらは確かにそれを裏付ける事実が過去にありました。
槍や薙刀が剣術の三倍強い
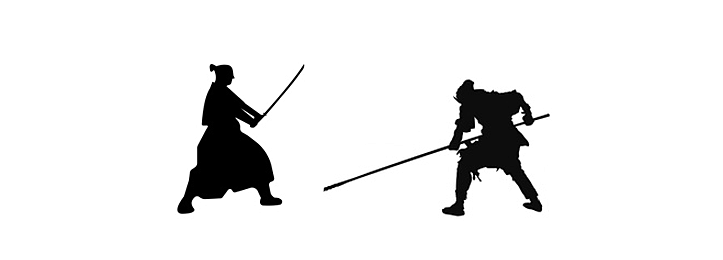
明治時代の撃剣興行において、園部秀雄という薙刀の女性師範が、渡辺昇を始めとする非常に有名な剣道家を片っ端から破っていった史実が残っており、この事実に端を発しているようです。
渡辺昇は幕末期に幕末江戸三大道場の一つと言われた練兵館の塾頭を務め、京都では何度も人を斬り新選組をも恐れさせたといわれる剣豪です。
その園部師範はその生涯において、なんと渡辺昇の秘蔵弟子である堀田捨次郎という若い剣士との試合と契り木の使い手による奇襲をくらった試合の二回以外、負けたことがないとか。
詳しくは以下のWikipediaを参照されたい。
>園部秀雄
園部秀雄についての話と「契り木」という武器についてもう少し知りたい方は以下のサイトの中段あたりをご参照ください。契り木の実際の使われ方も映像で見ることができます。
そして、論より証拠。
以下は「注目の動画」ページでも紹介している現代剣道と現代薙刀で実際に闘ってみた異種試合の映像です。
実際剣道五段の副将の人が、あまり強そうに見えない女性にあっさり二本とられて負けています。
やっぱり足は現代剣道の有効打突範囲にないので長く剣道をやっている人ほど反応できないのではないでしょうか?
また相手は届かない遠間から打てるという点が圧倒的に有利。
これが真剣だったらもう結果は語るまでもない気がします。
梶原一騎説の場合、実際どうなの?
では話は冒頭の話に戻り、一般に広く知られるようになった無手の空手や柔道は剣道に対してそれほど実力差が必要か否か?という点について論じてみたいと思います。
私は剣道経験6年の剣道二段、極真空手経験二年半で六級(黄帯)というぐらいのつたない経験しかありませんが、それでも三倍段はオーバーじゃないと思います。
竹刀なら二倍段で、木刀なら三倍段、真剣なら三倍段どころか六倍段ぐらい必要に思えます。
竹刀でも二段以上の腕があれば相当な打撃力がありますし、剣道の打突のすさまじいスピードはたとえボクサーの動体視力を持っていたとしても到底追いつけないでしょう。
加えてリーチがあるのですから防ぐのは至難の業。加えて竹刀でも突き技は超危険です。
ただ極真に代表されるフルコンタクト空手であれば相当打撃に対して強い肉体に鍛え上げられているので正面からの突きを食らわなければ竹刀の打撃を手足でガードしてつっこみ体を浴びせてショートパンチやひざげりへとつなげる戦法を考えた時、二倍段ぐらいでいけるのではないかと考えました。
しかしそれが木刀になった場合、その威力は真剣とさして変わらないため、ガードした手足も一撃で骨折せしめることが可能。さらに、頭、首、ボディに一撃でもまともに入れば骨折どころか重症は無論のこと、死に至る可能性も少なくありません。
それがさらに真剣ともなればかすっただけで血しぶきが舞いますし、一振り体はかわせても指なんか薙いだだけで簡単にポロリ落ちるわけですからもう素手で立ち向かうことがいかに危険かわかろうというものです。
ただ真剣は相当重いので竹刀のように器用に振り回せなくなりスピードはかなり落ちるため、いったん振らせてからいかに一瞬で間合いをつめて重い一撃を与えられるかどうかが勝負の分かれ目になるのではないでしょうか?
武士の時代のテレビドラマなどを見ていても、素手の武士が真剣をもった相手に立ち向かう際、刀をかわし一瞬で懐に入った後で勝負を決していますが、あれを実現するには相当の胆力、実力差がないと無理でしょう。
もし自分が戦うとしたら
では試しに、剣道二段以上の有段者が本気の殺意をもって真剣を手にし、目の前で構えている姿を頭の中で想像してみてください。
それに対して素手の自分がどう戦うか考えてみましょう。
というわけで自分でやってみた結果私の結論は・・・
全力を振り絞って走って逃げる!
これしかありませんでした(笑)
ちなみに逃げる前に、小石拾って投げつけ、注意をそらしてから逃げるぐらいがせいっぱい。
小石さえない場合でも足元に砂があればそれをかき集め目つぶしか煙幕的に使うとか・・・。
というわけで、いかにかっこ悪くてもとてもまともに戦う気になれません。
まぁ周りで大勢の人が見てたり、好きな女性が見てたりしてたらもう死んだと覚悟して闘うかもしれませんが、勝負の場で敵と二人っきりなら間違いなく即効で逃げます(笑)
あとは極真空手で全国大会優勝経験ぐらいの実力があれば戦えるかもしれませんね。
さてあなたならどうしますか?
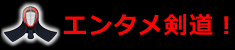












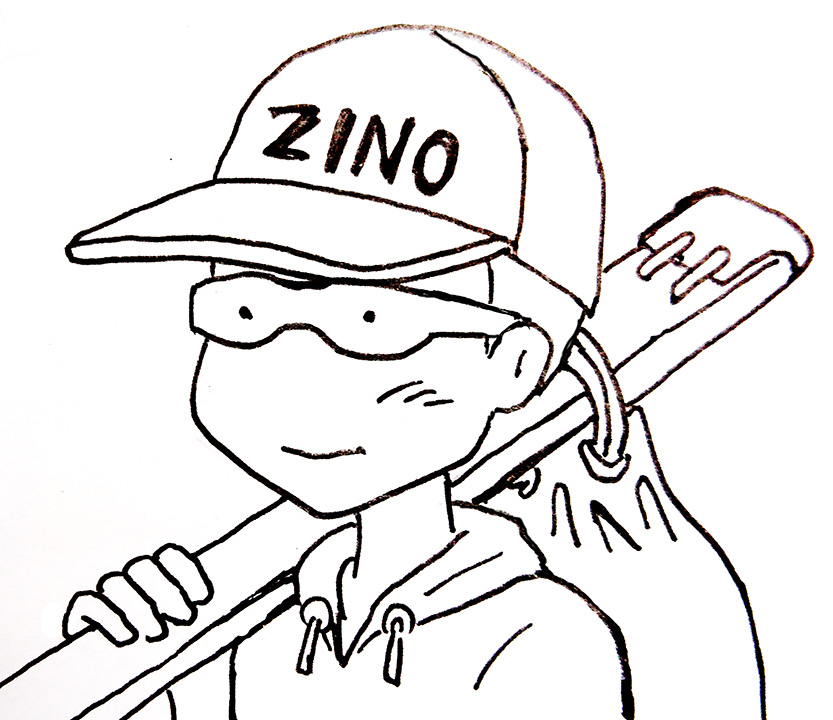



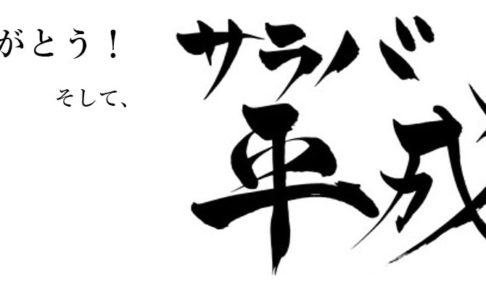

コメントを残す