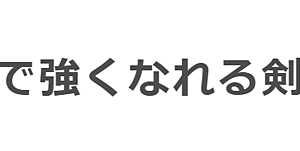老齢になっても本当に若者に勝てるの?という疑問への考察(2)
老齢になっても本当に若者に勝てるの?という疑問への解として、実際にいた人物として前回よりさらに昔、今回は幕末の人物に光を当ててみたいと思います。
ご紹介するのは、白井 亨という人物ですが、これは小説家として名高い戸部新十郎の著作「日本剣豪譚(幕末編)」から引用したものをさらに部分的に今の人にはわかりづらい昔の言葉の部分を読みやすく修正し、あまり必要ない部分についてははしょっています。
戸部新十郎は、日本の剣界の歴史をよく研究され、史実に基づいた上で行間を創作で上手く埋めており、メジャー雑誌の「月刊 剣道」などでもよく引用されるなど信頼性が高い作家として、有名で人気作家でした。(今はもうお亡くなりになっているので過去形)
つまり過去の資料の史実に基づいているとはいえ、物語化するためにある程度創作された部分もあるので、その点についてはご了承ください。
今回ご紹介する白井 亨という人は、老年期においても達人の域にあって強かったと史実に記録が残っているので、今回ご紹介するわけですが、面白いのが今回のテーマを体現した本人自体がそのテーマへの解を探し続けたという点です。
ちと長くなるので、今回はテーマについて当人の転機となるクライマックスシーンへ至る前半部分をご紹介したいと思います。
幕末の剣士 白井 亨
中西派一刀流の道場を代表する剣客で「中西門三羽烏」と言われた内の一人に、白井 亨(しらい とおる)という人物がいた。

この頃の中西派一刀流と言えば、千葉周作、山岡鉄舟、浅利又七郎義信といった多くの名剣士を生んだ、江戸後期から幕末、維新にかけ、まさに剣道界の中核という存在であり、下谷練塀小路東側に多くのも門人を抱え江戸随一といわれる大道場だった。
あの勝海舟が、この白井 亨という達人に、自身が剣道修行時代、年にして二十歳の頃、教えを受けたというが、後年次のように述解している。当時彼とは四十は年が離れていたというのですでに六十の老年であった。
「この人の剣法は大げさにいえば、一種の神通力を具えていたよ。彼が白刃をふるうて道場に立つや、凛然たるあり、神然たるあり、とても侵すべからざるの神気、刀尖よりほとばしりて、真に不可思議なものであったよ。おれらは、とても真正面には立てなかったさ」
海舟は、この老剣士の境地に到達せんものと、懸命になって修行したらしい。
「惜しいかな、とうていその奥には達し得なかったよ。おれは不審に堪えず、このことを白井に訊ねると、白井は聞き流して笑い、それは御身が多少、剣法の心得があるから、私の刃先を恐ろしく感ずるのだ。無我無心の人には平気なものだ。そこがいわゆる剣法の極意の存在するところだよ、と言われた。おれはそのことを聞いて、そぞろ怖れ心が生じ、なかなか及ばぬと悟ったよ」と。
しかし老齢となってもこう言われるほどの境地に達するまで、白井自身、幼少の頃から兵法の道を究めんがため苦悩の連続だった。
元々体は幼年期は小さく成人になっても並の体格だったため、自分が世話になったどの道場、流派でも大柄で筋骨たくましい男の方が幅を利かせているのを目の当たりにし、「兵法とはこんなものなのか?五尺(150センチほど)の小さい体格のものが大きな体格の者を、また三尺の利剣をもって剛力を打ち倒すべきものではないのか?」という嘆きともいえる疑念を常に持っていた。
八歳の頃、最初に入門した流派の道場では、毎日七百回素振りをし、きびしい稽古に七年続け、十四の頃には師匠に認められる大きな体格のものにも負けぬようになっていたのに、師匠からは納得できるような言葉は何も得られなかった。
そこでここにいてもこれ以上何も得るものがないと悟ったのだろう。十五になった時に当時三代目中西子啓がしきっていた高名な中西派一刀流の門をたたいた。
入門し、十九歳までの5年間死にもの狂いで努力するが、ここでもまた体の強大なものが強く、力の強いものが勝つ、という何の妙味もない実態に、打ちひしがれてしまうのである。
自分は朝早くから夜遅くまで稽古に励み、入門してからというもの、どんなに体の具合が悪くても、熱があろうと一日も道場通いを休んだこともなく、形や試合の量は人の倍は行った。さらに夜は重く大きな木剣をびゅんびゅんと振りまくった。
それでもなお、巨躯強力の者が強い、という結果がなんとも情けなく、いっそ剣をやめてしまおうかとも考えていた。
その疑念を師の子啓に機会をみては訊ねたが、単に「挙動疾斉、軽足便捷、気息壮にして、四肢形体は健剛なることを要す」というばかり。
周囲の人も別段、疑義もなさそうだった。
師の子啓は容貌に威厳があり、肚が太く、寛大であり、弟子も三千人ほどいて諸大名も争って兵法の師としてあがめるほど。その名は天下に轟いている。
こんな人物だが、亨を納得させてくれない。
しょせん、<兵法とは何か、どうあるべきか>という根本命題について何の解決も与えてくれないのだった。
その頃、寺田五右衛門宗有という人物が先輩にいた。入門の先後や老若の差異はあっても、同門の朋友である。彼は組太刀専門の者で、帰り新参だった。二代目子武が導入した竹刀、防具稽古に反対して、一度中西門を去り、三代目子啓になってふたたび戻ってきたのだ。
この彼と後年、勝負する中で、自分の求めてきた兵法の道に光明を見出し、師弟の関係となるのだが、この頃はまだ宗有も修行中であり、兵法の境地に達するため模索の日々を送っていた。
この先輩がときどき子啓と兵法について論じ合っていたが、結果は一致しない。
議論の一つは、「組太刀・型」がいいか、「竹刀、防具稽古」がいいかということだった。
これはしかし稽古の形態に過ぎない。論ずるまでもなく長所短所を認め合いながら、それぞれの形態で稽古しているのが現状だった。
今一つは、「形勢(技法)」と「真理(心法)」についてである。
子啓の教示によれば、ひたすら技法を学び、体得することにある。が、宗有の教えによれば、技法・心法が相半ばしていた。
「その美(優れたるところ)、いずれあることを知らず」と亨はしるしている。
宗有は中西門を脱した後、「谷神(こくしん)伝平常無敵流」を学んだ。「谷神伝」とは、老子のいう「谷神不死」ということで、一切万物生成する天地の働きである。
当時まだ、宗有はその至極の道を研究中だったので、技・心折衷というあいまいな表現しかとれなかったのだろう。
後年、気・剣・体が一つに融合し、無心に流露する天真独朗の境地から、「天真伝一刀流」を創始する宗有も、争気ばかり旺盛で、道の根元にまず透徹していなかった、というわけである。
しかしそれでもすでに心法の重要性を知り、追求しようとしていたのはさすがというべきだった。
対して亨はこの頃まだ、この天地の道を知らず、同門の衆とともに、ただ飛んだり跳ねたりして刀を揮い、勝ち負けを闘鶏のごとく争っている有様だったのである。
その内、亨は、「八寸の延矩(のべかね)」という技を得た。

これは新陰流正統三代目を称した小笠原玄信斉が創始した技で、玄信斉が唐にいる頃、張良の子孫という者と、互いに芸返しをしながら「戈術(ほこじゅつ)」を習い、それをヒントにしたものと言われる。
中国戈術からの発生であり、中国武術にあるように、飛んだり跳ねたり、激しく七転八倒して動くらしいことが想像されるが、根本は「八寸の矩」にあり、直心影流明石軍司兵衛の伝書に、「八寸の延矩は、左右より打込むとき、上にて四寸、下にて四寸ずつ、八寸開くこと」とある。
(「矩」は、まっすぐなこと。直線。直角。 他に模範。手本。法則などの意味がある)
その実態は明らかにされていない。
結局、玄信斉の高弟でこれを伝授された針ヶ谷夕雲は、「妄想虚事」と言って排しているほどで、亨も後年「雑技」と言っている。
しかしこの雑技が、師の子啓が死んだおりに廻国修行に出た際、故国の備前で「奇なり」ともてはやされた。
そこで備前藩の下、逗留して軍学を学びながら諸士に兵法を教えることになり、その数三百人あまりで毎日道場にて稽古し、時には君侯の前で兵法を披露、滞在中は丁重に扱われたので、兵法者としてはまずまず幸せな日々が過ぎていった。
が、たちまちかつての疑念が頭をもたげるのである。
「幼い頃から兵法を学び、多少なりともきびしい修行をへて、いささかの雑技を得た程度のもので、いたずらに肉体を酷使し、いまだ従容として、敵を制するすべを知らない」といった反省からさらに、
「考えてみれば兵法を学んで二十年も経つ中で、優れた体格、気性、技量をもつ剣士を多くみてきたが、誰もかれも四十を過ぎれば、たちまち衰えてしまう。これはどうしたことか?兵法とは、それほど頼りないものだろうか?」と思い至る。
「兵法未知志留辺」では、次のように述べる。
「今をもって壮年でもいまだ身体手足が固くなっておらず機敏に動けるものもいないわけではなく技を活かす機会を得るものもいるが、五十前後の老年期にいたり、手足が固くなってくれば、現実のところもはやその剣技は活用できるレベルではなくなり、天下の剣客は皆同様の有様である」と。
この時、亨は二十八歳なのだが、年減れば、活用を失う兵法の道に入ったのは、一生の誤りだったと涙を流して嘆いていた。
しばらく兵学書を読み、憂愁をまぎらわせていたのだが、江戸の母が大病を患ったというので、すぐに江戸に帰った。
そして母の病が癒えると、元同門の先輩であり朋友の寺田宗有を訪ねた。
宗有は喜んで迎え、七年余の廻国修行の成果について訊ねたところ、亨は、かつての宗有の教えにあった、技法・心法が相半ばしていることに沿って、「疑念は疑念として、技術そのものは上がった」と答えた。
そこで宗有は微笑んで、「昔正しいと思っていたことが今正しいとは限らない。試しに立ち合ってみよう」という。
望むところと亨はこれに応え、二人は木剣を持って道場に出た。
ときに亨は二十九歳、宗有は六十三歳の老齢である。
さてさて、勝負はどうなるのであろうか?
長くなってきたので、続きはまた明日!(笑)
乞うご期待!!